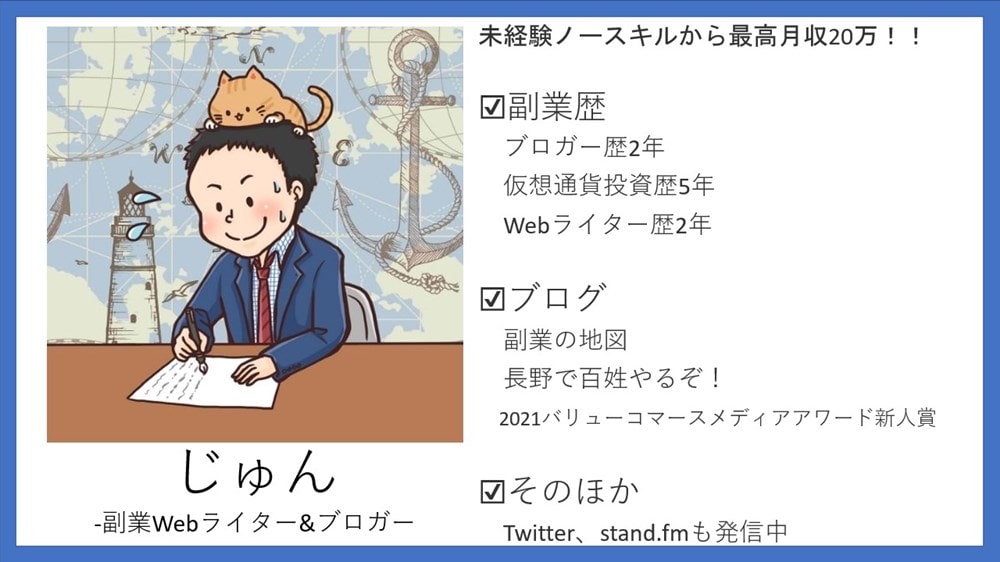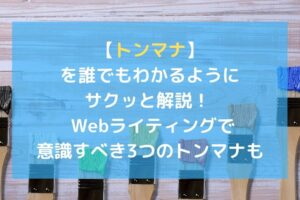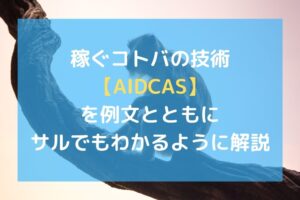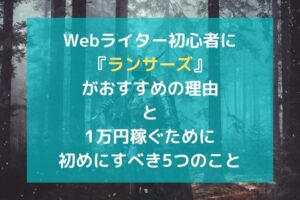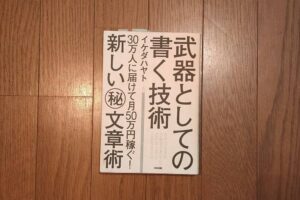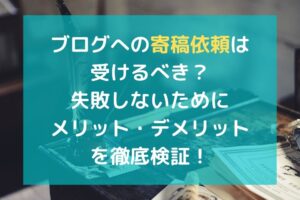アツシ
アツシトンマナってよくわかりません



イメージわかないですよね



あまり気にしないでいきます



トンマナは大事ですよ!簡単なんで意識しましょう
- トンマナってなに?
- トンマナはWebライティングに必要?
- トンマナの決めかたを知りたい
こんな悩みを解決します。
本記事の内容
- トンマナとは? | スターバックスコーヒーから学ぶ
- Webライティングにおけるトンマナの役割と必要性
- Webライティングのトンマナとは? | ドラえもんに学ぶ簡単な【トンマナ】
本記事では「トンマナとは?」を紹介します。
読み終えれば、トンマナを意識した読んでいて気持ちの良い文章が書けるようになります!
「トンマナ」について書きます。
トンマナとは? | スターバックスコーヒーから学ぶ





トンマナってなんですか?



トーンとマナーの略です
トンマナとは「トーン(Tone)」と「マナー(Manner)」を略した言葉で、広告や雑誌などのデザインやスタイルに一貫性を持たせることです。
トーンとマナーには、以下のような意味があります。
- トーン:調子、色調、テイスト
- マナー:作風、様式、スタイル
わかりづらいのでぼくが良く仕事で使うカフェ、スターバックスを例にしてみます。
スターバックスコーヒーは印象的なみどり色に、ギリシャ神話に出てくる怪物セイレーンが白く描かれているロゴマークのイメージが世界中で定着していますよね。
(シアトルにある第1号店は、開店来の色調(茶色)とデザインを採用)


店舗内も落ち着いたブランドカラーのみどり色と茶色で統一されています。
みどり色には「安らぎ・癒し・穏やか」、茶色には「落ち着き・ぬくもり・安心」といった印象を喚起させるためリラックスできる空間になります。
また両方とも自然を意識させる色でもあり、相性が良いですね。
スタバでは、他にもコーヒーカップやストローなどに、緑色を配色しています。
他にも個人的に魅力的なトンマナだなぁと思うのが、
- IKEA(イケア)
- Apple(アップル)
- Uniqlo(ユニクロ)
あたりでしょうか。
デザインやスタイルに一貫性を持たせることが、トンマナを意識するということです。
デザインやスタイルに一貫性を持たせること=トンマナ
Webライティングにおけるトンマナの役割と必要性





トンマナは必要ですか?



ブランドイメージの確立などがあります
トンマナのデザイン面での1番重要な役割はブランドイメージを確立するためです。
一方、Webライティングでのトンマナの役割は
統一感のあるコンテンツを作って、コンセプトを伝えやすくすること
です。
統一感のないサイトや文章だとユーザーは違和感を覚えて読みづらいもの。
極端な例ですが、いきなりフォントや文字の大きさが変わったら読者はストレスを感じるでしょう。
そこでユーザーにとって心地の良いサイトを作るために、トンマナを統一することが必要なのです。
Webライティングのトンマナの役割は心地よいサイトを作ってコンセプトを伝えやすくすること
Webライティングで意識すべき3つのトンマナ





どうやってトンマナを統一すればいいですか?



具体的な方法をわかりやすく説明します!
Webライティングのトンマナとはなんでしょうか?
実際の例を見てみないと
トンマナを統一する
と言われてもわからないと思うので、次にわかりやすく解説します!
- 「です、ます調」か「だ・である調」か決める
- 〇〇を統一する
- NG表現や用語を設定する
項目は上記の3つです。
文章におけるトンマナは他にもたくさんありますが、キリがないので、非常に重要なものに絞って解説します。
3つの点を押さえておけばWebライティングに関するトンマナに関して、合格点は取れるでしょう。
1.「です・ます調」か「だ・である調」か決める





混ぜちゃいけないんですか?



ダメです!
文章を書くときは「です・ます調」か「だ・である調」か決めてください。
「です・ます調」か「だ・である調」が混ざっている文章をたまに見かけますが、非常に読みづらいです。
Webライティングにおいてトンマナは重要だ。
トンマナを意識しないと統一感がなく、読者にとって非常にストレスのかかる文章になるからです。
たとえば「です・ます調」と「だ・である調」がごちゃ混ぜの文章は、読んでいて違和感を感じるはずだ。
ストレスのかかる文章は読者に響かないし、読みづらいので、すぐに離脱をされてしまいます。
上記は極端な例ですが、自分で作っていても、イラっとするような文章になりました。
そこで以下のように「です・ます調」に統一することで違和感はなくなります。
Webライティングにおいてトンマナは重要です。
トンマナを意識しないと統一感がなく、読者にとって非常にストレスのかかる文章になるから。
たとえば「です・ます調」と「だ・である調」がごちゃ混ぜの文章は、読んでいて違和感を感じるはずです。
ストレスのかかる文章は読者に響かないし、読みづらいので、すぐに離脱をされてしまいます。
「です・ます調」は柔らかい文章を書きたいとき、「だ・である調」は堅い文章を書きたいときなど使い分けましょう。
また、同じ「です・ます調」でも、
より丁寧な「おります」「ございます」
や
「ですね」「です!」のようにもっとフランクで親しみやすく
することも可能です。
ブログなどのコンセプトや読んで欲しい読者のイメージに合わせて「です・ます調」か「だ・である調」を選ぶといいでしょう。
ちなみにぼくのブログはみてのとおり、軽い「です・ます調」で統一しています!
コンセプトや読者のイメージに合わせて「です・ます調」か「だ・である調」を選ぶ
2.〇〇を統一する





なにを統一するんですか?



言葉遣いや表記のルールです
Webライティングのトンマナでは以下の4つを統一するといいでしょう。
- 言葉遣い/テイストを統一する
- 表記のルールを統一する
- 構成と文字数を統一する
- 段落・改行を統一する
これらは「統一しないといけない」わけではありませんが、バラバラだと読者を混乱させてしまいます。
詳しく解説します。
a.言葉づかい/テイストを統一する



テイスト?



雰囲気やキャラですね
言葉づかいやテイストを統一するのがトンマナでは大事です。
言葉づかいやテイストがバラバラだと、読者に強い違和感を与えてしまいます。
たとえば、ジャイアンがのび太に対して
「ぼくは君に怒ってます。のび太君!ぶん殴らせてください!」
とか言ったら気持ち悪いですよね……
あるいはドラえもんが、
「のび太君、俺に任せろ!どこでもドアを使えば、しずかちゃんの風呂を覗けるぞぅ~」
とか言ったらどうでしょうか?
ちょっと極端な例ですが、言葉づかいやテイストの重要性をわかりやすく説明してみました(笑)
トンマナでは言葉づかいやテイストが一致しているか意識する
b.表記のルールを統一する



表記ってなんですか?



漢字、平仮名や全角半角などがありますね
トンマナでは表記のルールを統一することも意識しましょう。
表記には
- 漢字、ひらがな、カタカナ(時やとき、彼やカレなど)
- 全角、半角
- 言葉自体の表記(例:アイデア/アイディア、しゃけ/サケなど)
- 数字の点(1000か1,000か)
- 記号(!や?の使用の有無)
- 「」、『』や()の使い方
- 自称(ぼく、ぼくか自分かなど)
などがあります。
これらの表記は基本的には統一した方が読みやすい文章になります。
ちょっと専門的になりますが、SEOの観点や連チャンの重複表記を避けるために、あえて違う言葉を使うときは例外です。
ただ、まずは例外を意識せず、表記は統一すると覚えましょう。
最初に表記のルールを作っておくと便利
c.構成と文字数を統一する



構成と文字数を統一する?



おおまかにルールを決めましょう
構成と文字数を統一すると文章のスタイルが同じになるので読みやすいです。
たとえばぼくのブログでは、
- 1つの見出しに対して6文以上を続けない
- 1文はPCで書いたときに2行以内にする(約100文字以内)
などとルールを決めています。
上記のルールを守ることで1つの見出しはおおむね600字以内になります。
また1文が長かったり、短かったりとバラバラで、読者から「読みづらい!」と思われるのを避けることが可能です。
絶対ではないですが、基本的にはルールを守るように書いています。
構成と文字数を統一して読みやすく
d.段落・改行を統一する



改行も統一しないとダメですか?



その方が読みやすいですね
段落・改行は統一することをおすすめします。
1段落のボリュームや改行の頻度がバラバラだと読者が読みづらいから。
ぼくのブログでは、
- 句点「。」で改行
- 読点「、」は文が長いときに改行
- 強調したい文字があるときは前後で改行
としていて、あまり段落は意識していません。
ライター案件によっては3行以上は改行など、ルールがありますので意識しておくといいでしょう。
段落・改行も統一することで読者が読みやすいトンマナになる
3.NG表現や用語を設定する
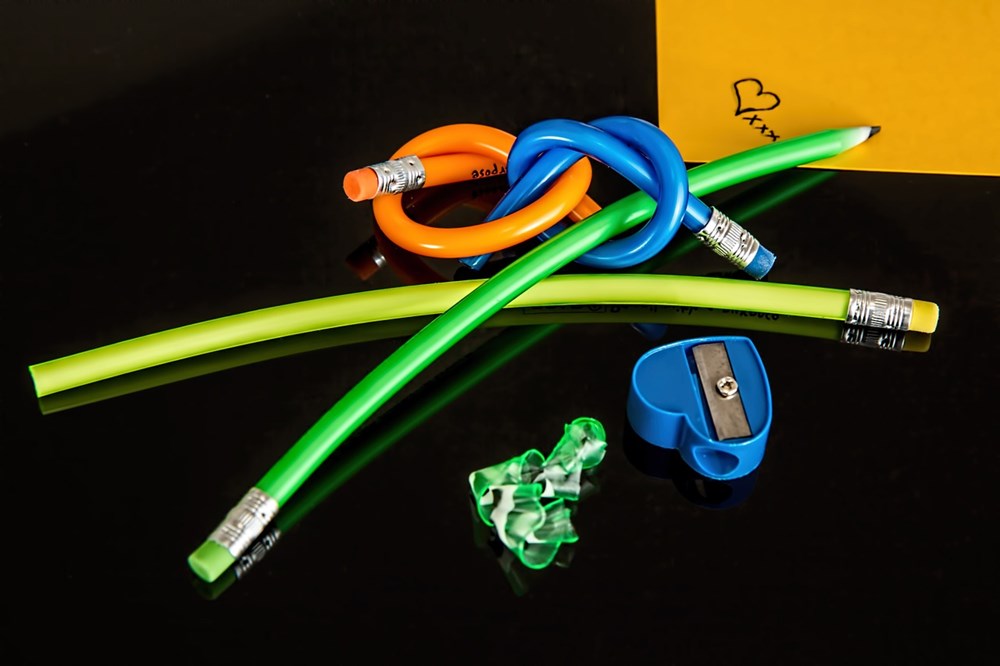
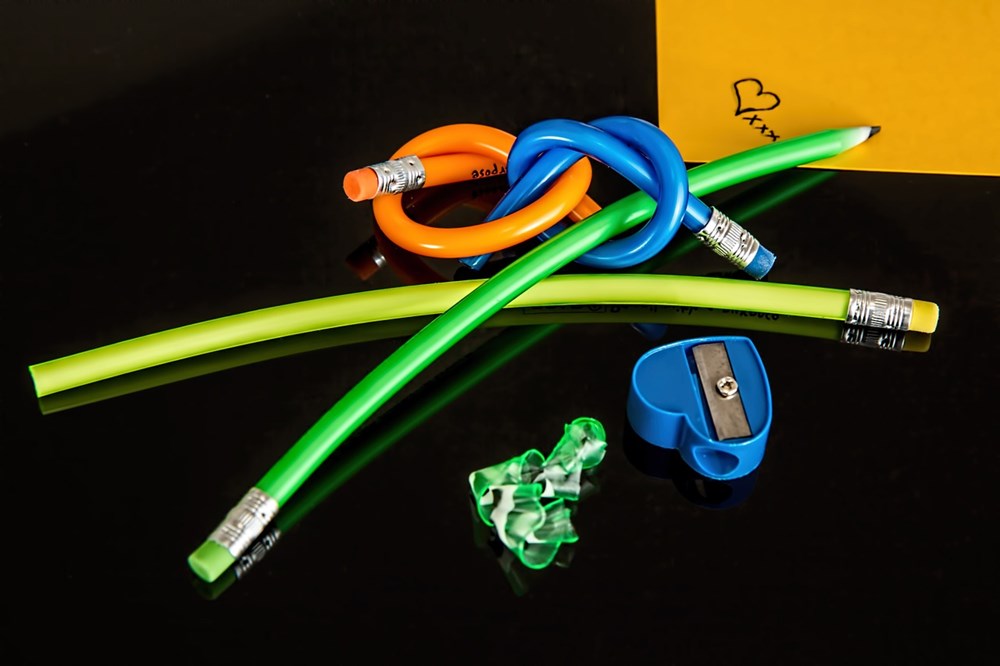



NG表現なんてあるんですか?



企業のライティング案件ではありますね
NG表現や用語を設定するのは主に企業がサイトや記事をライターに依頼するときに行われます。
NG表現を設定する理由は、
- 企業イメージを損う言葉を排除する
- 客観性のない主観的な表現になるのを避ける
- 誇大広告など不当な表示を避ける
ためです。
たとえば、「最高」、「最小」など最上級を意味する言葉や、「唯一」、「日本一」など優位性を意味する言葉は、法律も関係するので注意が必要。
ライター案件では、あらかじめクライアントから説明がありますので、神経質にならず「そんなこともあるのか」くらいに覚えておいてください。
また、個人的にはブログでライター案件でも、ネガティブな表現はしないようにしています。
これはせっかく読んでくれた読者にネガティブな感情を抱いてほしくないというぼくなりのルールです。
NG表現を設定することでマイナスを避ける
トンマナを意識して読んでいて心地よい文章を書きましょう!





トンマナ、わかりました!



頑張って使いこなしていきましょう!
本記事では、トンマナについて解説してきました。
重要なポイントをおさらいすると下記のとおりです。
- トンマナとはデザインやスタイルに一貫性を持たせること
- Webライティングにおけるトンマナは統一感のある文章を書くこと
- 「です・ます調」か「だ・である調」を決めるのが最初のトンマナ
副業Webライターじゅんから「トンマナ」について宿題
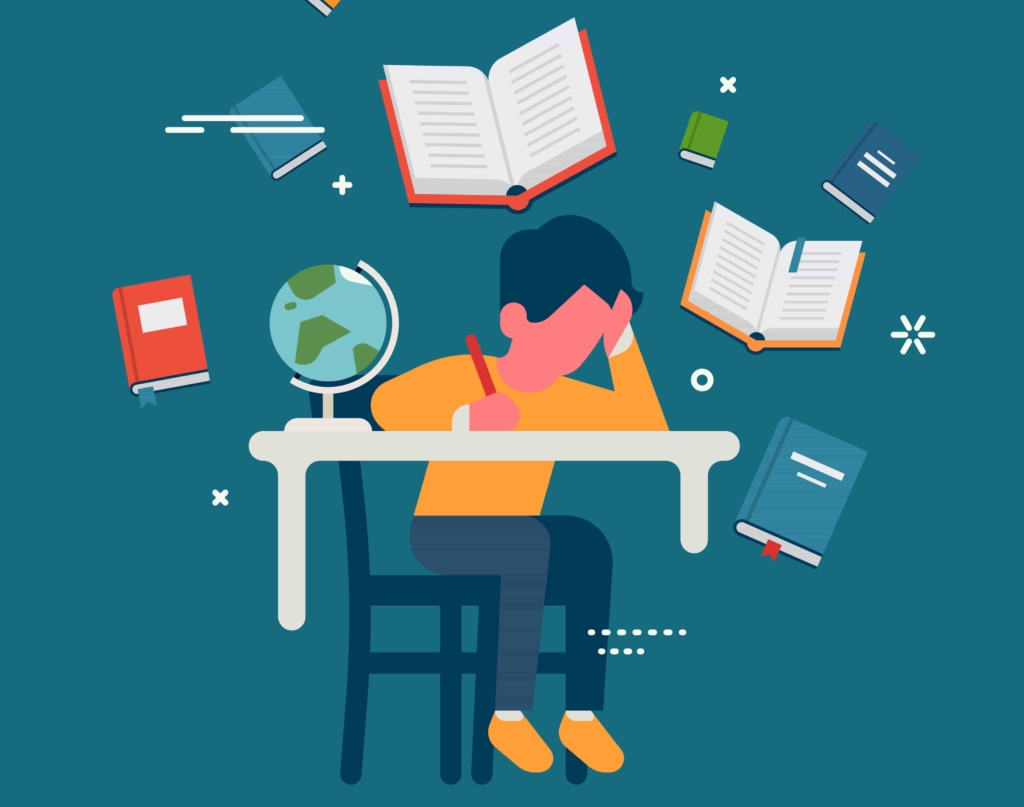
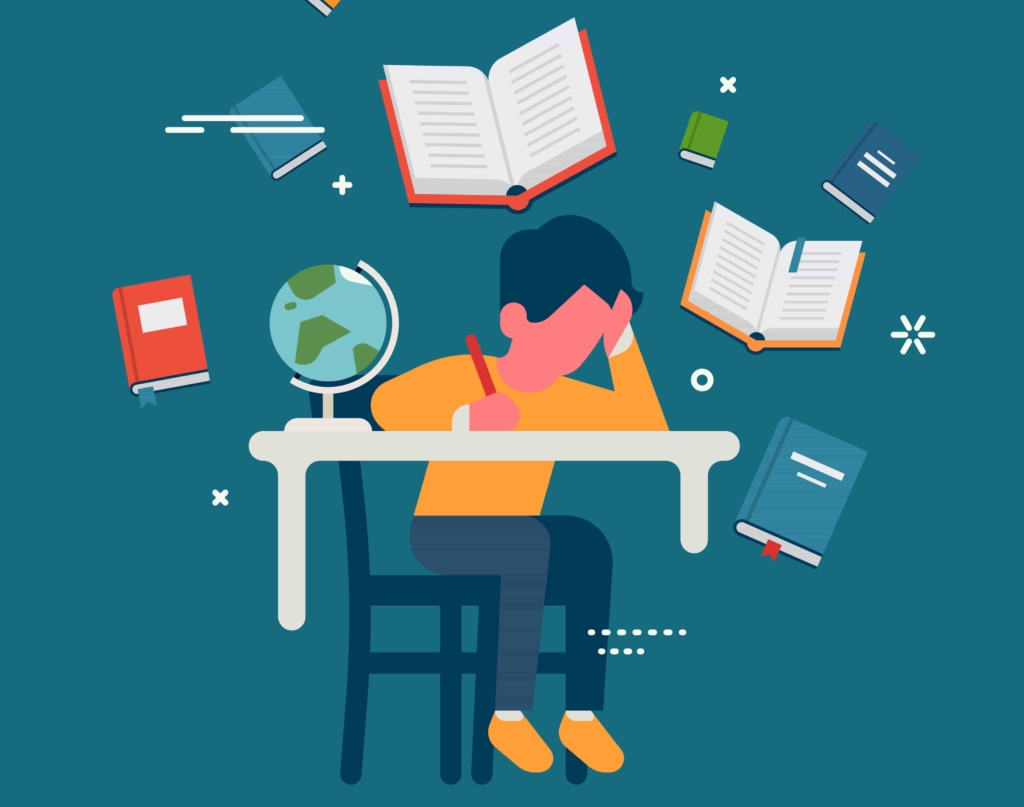



せっかくこの記事をここまで読んでくれた人に忘れないように宿題を出します‼
- 好きな企業のトンマナをリサーチする
- Webライティングでのトンマナの役割と必要性を復習する
- 3つのトンマナを意識してライティングする
Webライティングで手が止まってしまう人は、「Webライティングで手が止まる人は【PREP法】だけ学べ!」の記事にまとめてあります。
読んでおくと文章がスラスラ書けるようになりますよ!





ここまで読んでくれてありがとうございました‼


ライティングに迷った時は当ブログ「Webライターの地図」を思い出してくれるとうれしいです。
あなたに方向を指し示せる地図のような存在になれるよう更新を頑張っていきます。
それでは素敵なWebライターライフをお過ごしください。
ではでは‼